« 2011年01月 | メイン | 2011年03月 »
2011年02月28日
2011年2月27日 しもつかれ
郷土料理には、その土地の雰囲気、歴史、伝統などがよく出ているものです。
今日はJAの直売所で栃木県に伝わる郷土料理の「お総菜」が販売されているというお話しです。
「栃木県・塩谷郡(しおやぐん)」「高根沢町(たかねざわまち)」
にあります「うまい屋」の田村悦子さんにお話を伺います。
◎ はじめに高根沢町に関して教えて下さい。
栃木県のほぼ中央に位置し、緑豊かな土地で水田地帯が広がっており、
特産品はイチゴやお米です。
◎ うまい屋は、JAの女性組合員で運営しているそうですが、
どのようなことをされているのか教えて下さい。
町内にある「JAしおのや」の農産物直売所の一角で「うまい屋」の名前で地元の
食材を使ってお惣菜を販売しています。
地元の郷土料理を残していこう!と、JAの女性組合員、6人で運営しています。
◎ そちらでは、いまの時期の名物料理があるそうですね!
栃木県の郷土料理「しもつかれ」
店では、年末~3月頃まで提供する名物料理です。
地元では2月の初午の日に、正月用の塩ザケの頭と節分にまいた豆の残りを使って
作り、わら筒に入れ、赤飯とともに、神様にお供えします。
うまい屋では、鬼おろしで大根とニンジンをおろして鍋に入れ、そこにサケの頭、
大豆、油揚げを加えます。最後に酒かすを足し、さらに煮ていきます。
◎ お客さんの評判は、いかがでしょうか?
宇都宮辺りからのお客さんも多く、一度買ったお客さんは、
「懐かしい味」「美味しかった!」などと言ってリピーターになってくれます。
◎ 今後も新たな展開を考えているそうですが・・・
今現在は、お惣菜しか作っていないので、地元のお米を使ったおにぎりやお弁当
を作ろう!と準備を進めています。春おすすめは、ふきのとうの天ぷら&ふき味噌です。
◎ おしまいに、田村さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。
野菜中心で、バランスが取れた食事をする事です。
投稿者 joqr : 12:27
2月27日ゲストは、株式会社タニタの栄養士、荻野菜々子さんです。
ゲストは、いま話題の本、「体脂肪計タニタの社員食堂」
でおなじみ、株式会社タニタの栄養士、荻野菜々子さんです。
荻野菜々子さんは1982年、東京のお生まれ。
女子栄養短期大学を卒業後、2005年、株式会社タニタに入社。
社員食堂のスタッフとして、低カロリーで健康的なメニューを数多く考案されてきました。
現在、社員食堂のメニューを紹介した「体脂肪計タニタの社員食堂」が発売中。
各メディアで話題の一冊です。
荻野さんには、ダイエットにも寄与するタニタの社員食堂メニューの特長、
具体的な人気メニュー、などについてお話を伺いました。
投稿者 joqr : 12:22
2011年2月28日 温かな霧に包まれて
息子の受験慰労を兼ねて温泉に行った。
近頃は1泊しなくとも、日帰りで天然温泉に浸かれる。
客側のニーズに合わせ、様々な形態に応えてくれるのだ。
彼のリクエストで、何度か行ったことのある、
硫黄の香りがする湯を目指した。
「ゆ」・・紺地に白く染め抜いた暖簾の切れ目に頭を潜らせる。
いつもだと大賑わいの脱衣所は驚くほど静か。
まるでエアポケットのようだ。
20近くある唐編みの籠が全部伏せてある。
ニコニコしながら、競うように服を籠に放り込む。
浴槽へ通じる引き戸を開けた。
あっという間に花火の残り香に似た霧に包まれる。
桶に手をやった。
「カラン!」という音が壁に当たる。
それは湯気に包まれ、少し丸くなって戻ってくる。
早く肩まで沈みたい・・・体を洗う行為ももどかしい。
その時、お互いどんな単語が発せられるだろう。
いよいよ湯船に足を入れる。
共に「うお~!!」という雄叫び。
それは、正確に言えば驚きと忍耐の表現だった。
60度近い源泉は加水されているとはいうものの、
冷えた体には一瞬火傷するほど熱く感じたのだ。
10秒ほど耐え、そろりそろり体を沈める。
湯面が首に近づく頃には体がほぼ馴染んでいた。
去年までの彼ならば、他に客がいなければ迷うことなく温泉水泳大会。
それが今回は首の後ろを揉みながら湯をかけている。
15歳のその行為は、大人しいというか爺臭いというか・・・
「泳がないのか?」
思わず聞いた。
「あはは、温泉の良さが分かってきたと言うのかな・・」
何という台詞だ!?
湯気の中、じっくり浸かる息子をながめながら思った。
「大人への階段を上がっている・・・か」
帰りの車中、堪えきれず助手席で眠る息子を見つつ、にんまり。
「おい、まだまだ階段はあるぞ・・・俺も上っている最中だ」

ほっとする
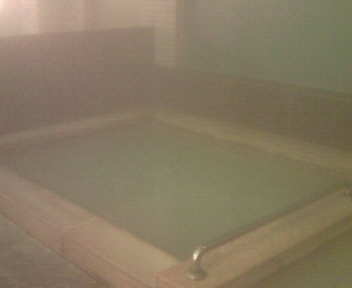
温かな霧に包まれて

癒しの源

湯気の行方
投稿者 joqr : 09:00
2011年02月21日
2011年2月20日 里芋の団子汁
今回は、番組リスナーのみなさんの「我が家の『よい食メニュー』をお伺いいたします。
埼玉県・所沢市にお住まいの横山一江さんです。
◎ 横山さんは、農家をされているそうですね?何をつくっていらっしゃいますか?
夫と一緒にほうれん草と里芋を育てています。
自分のところで採れた野菜を漬け物にしています。
野菜だけではなく、庭に梅の木もあり梅干しも自家製。
漬け物と梅干しは友人にあげたり、何か集まりがある時にはお茶請けとして、
持って行きます。
◎ 漬け物、梅干し、美味しそうですね。
他にも「よい食メニュー」があるそうですが・・・。
「里芋の団子汁」
里芋は普段、煮っころがし等にするが、それだと飽きてしまうので、汁物にします。
◎ 使用する材料を教えて下さい。
里芋、鶏のひき肉、ねぎ、しょうゆ、その他調味料。
◎ 「里芋の団子汁」の作り方を教えて下さい。
はじめに里芋の皮を剥きやすいように、レンジで温める。
里芋は、潰してそこに片栗粉を混ぜて団子状に!
鶏のひき肉もつくねにする。
里芋の団子とつくね、ねぎを一緒に煮て、しょうゆで味を調えて、できあがりです。
◎ ご家族の反応はいかがですか?
里芋の団子は、食感がつるっとしていて、美味しいと好評です。
◎ おしまいに、横山さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。
年齢を重ね、野菜中心の食生活を心掛けている。あと毎朝、ヨーグルトを食べています。
投稿者 joqr : 17:56
2月20日ゲストは、毛利眞人さんです。
ゲストは、音楽ライターで戦前・戦中のジャズに
関する研究家、毛利眞人さんです。
毛利眞人さんは1972年、岐阜県・郡上八幡のお生まれ。
高校生のころからレコードのコレクションをはじめられ、
地元新聞に音楽に関する執筆をはじめられました。
音楽の中でもとくに戦前のジャズ、ポップスに関して詳しい
研究・執筆をされています。
現在、NHK「ラジオ深夜便」のSPレコード・コーナーで選曲、
構成を担当。
また、日本における戦前・戦中のジャズに関する研究を
まとめられたご本「ニッポン・スウィングタイム」が
講談社から発売中です。
毛利さんには、SP盤収集の苦労話などをお聞きしたほか
ご自身のコレクションからジャズの名曲を選曲いただき、曲の解説とともに
番組でご紹介していただきました。
投稿者 joqr : 16:32
2011年2月21日 フランスの香り?
2月は我が豚児の誕生月である。
重ねて、彼は今月高校受験だった。
2月前半生まれは、受験の年、
誕生会どころではない気がする。
反面、誰よりもドラマチックなバースデーになる。
我が家といえば・・・。
望み通り!
とはいかなかった。
でも、失意のどん底とも違う。
思い起こせば、私の高校受験は・・・
大失敗。
自分よりも周りが意気消沈したのには驚いた。
母が寝込んだ。
初めて「自分だけの人生では無いなあ」と感じた。
家族の、そして周囲の協力があってこそを痛感。
それに比べれば、息子の受験ドラマは、
微熱ですんだ風邪のようなものだ。
「誕生日と受験記念はなにがいい?」
息子に聞いた。
「自転車がいい」
「自転車なら、あるだろ?」
「うん、クロスバイクが欲しいんだ」
「何だ?それ」
「ロードバイクとマウンテンバイクのいいとこ取りだよ」
「具体的には?」
「先ず車体がママチャリより軽い。そしてタイヤが細い」
「そうだと?」
「ギヤも細かいから、アップダウンにも対応できて、遠くまで行ける」
「弱点は?」
「接地面が少ないから安定性に不安。特に雨の日」
去年まではこんなに理路整然とこたえなかった.
この1年でまた成長した様だ。
自転車屋に行った。
親に気を遣ってか、安い方から選ぼうとする。
係の人にアドバイスを受け、自分に合う自転車を決めた。
3万円ちょっとした。
車に積んで家に持ち帰った。
「お前、黒じゃなくてよかったのか?」
「うん、少しでも周りから気がついて貰わないと」
「だから黄色にしたのか?」
「あはは、目立ちたいしさ!」
いいやつだと思った。
『親は交通事故を心配する。
だから、自転車は目立った方がいい・・・。』
息子の洋服は黒ばかり。
「おい、この自転車に名前つけようか!」
「もう決めてるよ」
「お!何だ?」
「イエモン」
あえて由来は尋ねなかった。
いい名前だと思った。
3日に一度は空気を補充しないとならない、
フランス式のタイヤである。
語尾が上がる発音をした息子。
早速あたりを1周。
息子の背中が少しだけ大きくなった気がした。

フランスの香り?

ライトと泥よけは私が・・・
投稿者 joqr : 10:30
2011年02月14日
2011年2月13日 ゲストは、塩見利明さんです。
ゲストは、愛知医科大学教授で「眠り」に関する専門家、塩見利明さんです。
塩見利明さんは1953年、京都府のお生まれ。
愛知医科大学を卒業後、アメリカ・スタンフォード大学の研究員などを経て、
現在は愛知医科大学睡眠科教授の役職につかれています。
長年、「睡眠」に関する研究をされ、「日本睡眠学会 副理事長」でもいらっしゃいます。
現在はジャーナリストの鳥越俊太郎さんとの共著「眠って生きろ」が発売中です。
塩見先生には、睡眠に関する正しい知識をお話いただいたほか生活習慣の観点での睡眠の重要性について語っていただきました。
投稿者 joqr : 17:53
2011年2月13日 武蔵野食文化推進者
その土地に伝わる伝統料理を次の世代に語り継ぐ!とても大事なことです。
埼玉県のJAいるま野では、伝統料理を次世代につたえていくための「武蔵野食文化推進者」という取り組みがスタートしました。
「埼玉県JAいるま野」、「生活福祉課」の田中愛さんにお話を伺います。
◎ はじめに「武蔵野食文化推進者」とは何か? 教えて下さい。
この制度は登録制で、基本的にJA女性部のメンバーが登録しています。
地域に昔から伝わる郷土料理を次世代に残していこうと、メンバーが講習会などを
開き、料理を教えています。
次世代に伝統料理を伝えることが目的です。
◎ 現在は何人ぐらいの方が、登録していますのでしょうか?
50~60代の女性が中心で、現在20名以上が登録しています。
この取り組みは、平成14年からはじまったものです。
農家の主婦だけではなく、一般の主婦もいます。
◎ 近々、講習会を実施するそうですね!
年2回、大きな講習会を実施しています。
次回は3月を予定していて、そこでは入間市に伝わっています「ゆでまんじゅう」「呉汁(ごじる)」「ホウレンソウの白和え」の3種類を作る予定です。
◎ この制度の評判はいかがでしょうか?
地域によって料理の呼び方や作り方が多少違うので新たな発見が毎回ある。
料理だけではなく、情報交換の場としても役立っています
頑張って、いつまでも入間の味を受け継いでいきたい!
◎ おしまいに、田中さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。
普段どうしても食生活が偏りがちなのでバランスのとれた食事をするように心がけています
投稿者 joqr : 16:39
2011年2月14日 無音
2月11日、建国記念の日に降った雪、
夜には、枝を白く肉厚にしていた。
公園は雪特有の静寂に包まれている。
音で表現するなら「シーン」。
耳の奥で無音の際に聞こえる、あの音だ。
無音の有音に気づいたのは、今から36年前。
高1の春休み。
級友の祖父がいる迦葉山(かしょうざん)の寺でだった。
早朝に組んだ座禅。周りは雪景色。
初めての体験で、初めのうちは気持ちが落ち着かない。
そのうち、心が丹田に下がっていった。
周りの音は何もないはず。
しかし、耳の奥では「シーン」という音がしている。
「何で音に聞こえるのだろう・・」
すると、右肩に警策がずしり。
首を左に傾けると「パーン!」
心のゆるみに鞭打たれた。
「ああ、あの時の音だ・・・」
「バサッ!」
今度は肩に白い警策が落ちてきた。
翌朝、無音の世界はなかった。
朝日と共に尾長鳥が賑やかに挨拶をしていた。

無音

白い朝

透明な蓑虫

白とピンクと青空と
投稿者 joqr : 10:30
2011年02月07日
2011年2月6日 ゲストは、文筆家の白洲信哉さんです。
ゲストは、「白洲家としきたり」というご本を書かれた、
文筆家の白洲信哉さんです。
白洲信哉さんは1965年、東京のお生まれ。
父方の祖父母が実業家の白洲次郎・随筆家の白洲正子夫妻。
また、母方の祖父が文芸批評家の小林秀雄というルーツを
もたれています。
大学卒業後、イギリス遊学を経て細川護煕氏の公設秘書として
活動。
現在は、日本の伝統文化や展覧会のプロデューサーとして活躍
をされています。
また、文筆家としてこれまで書かれたご本に「白洲次郎の青春」
「白洲正子の宿題」などがあります。
白洲さんには、祖父母の白洲次郎さん・正子さんとの思い出や
日本に古くから伝わる伝統文化や行事について、本来の考え方を語っていただきました。
投稿者 joqr : 14:01
2011年2月6日 食育アドバイザー
東京にも、江戸時代から伝わる伝統野菜があります。
都市化によって種類は少なくなってしまいましたが・・・。
今日、ご紹介するのは、生産者の努力によって「復活」に成功した東京の「伝統野菜」です。
「東京都・立川市」「東京都農林水産振興財団」で「食育アドバイザー」を務め
ていらっしゃいます大竹道茂(みちしげ)さんです。
◎ 今日ご紹介して頂ける野菜は、何という野菜でしょうか?
「三河島菜」という葉物の野菜です。
江戸時代から明治時代まで東京都内で栽培されていたもので、場所は現在の荒川区。
常磐線に「三河島」駅があります。
白菜が中国から入っていた事によって、徐々に衰退してしまった・・・。
◎ どのようにして三河島菜を復活させたのですか?
この野菜は、絶滅してしまったと考えられていたが、仙台の種苗屋さんが、
代々引き継ぎ種を残していた。
仙台の書物によると、この種は江戸時代参勤交代で足軽が江戸の町から伊達藩、
現在の仙台に持ち帰ったものだった。
仙台では「芭蕉菜」という名前で呼ばれていた。
その種を分けてもらい、三河島菜を復活させました。
◎ 三河島菜の味の特徴を教えて下さい。
葉は黄緑色で長さ50センチ以上と大きくて軟らかく、クセがない。
漬物用菜っ葉や、今回新たに麺に練り込んだり、
餃子の具や炒め物に使ったりしたところ好評でした。
◎ 早速、地元の方から反響があったそうですね!
今年の収穫は終わってしまったが、4つの小学校からぜひ三河島菜を育てたい!
と声があり、来年度は学校給食にも提供する予定です。
◎ おしまいに、大竹さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。
伝統野菜は時期が限定されているので、その時期にあわせて旬の野菜を食べる
ことが大事だと思います。
投稿者 joqr : 14:00
2011年2月7日 春を待つ館
節分が過ぎ、暦の上では春を迎えた。
都内の梅が咲き始め、手袋・マフラーが必携だったのが
つけないでも我慢できるようになってきた。
そんなとき「春になっていくのだなあ」と感じる。
一方で、世の中の受験生は、すぐ先の春を求めて最後の一踏ん張りを見せている。
学問の神様、菅原道真が祀られている亀戸天神に足を運んだ。
午前9時前、社務所は開いているものの
ぽつりぽつりと地元の参拝客しか来ない時間。
太鼓橋を2つ渡って社殿へ向かう入り口で驚いた。
5年ぶりに訪れたそこの左斜め後方に、
あの東京スカイツリー(現在は約570メートル)がそびえ立っている。
改めて世界一の自立塔634メートルになる高さに感動。
境内の絵馬を眺めれば、参拝したたくさんの夢に出会う。
梅が咲き始めていた。
絵馬に託したそれぞれの願いが皆叶うといい・・・
そう思った。

春を待つ館

望みの象徴

花開く
投稿者 joqr : 10:06