« 2010年07月 | メイン | 2010年09月 »
2010年08月30日
2010年8月29日 新潟県・三条市
お米の消費量が、残念ながら少なくなっている中、様々な方法で消費を伸ばそう
という動きがあります。
今日ご紹介するのは、週5日間、地元のお米だけを使用して、小中学校の給食を
提供している新潟県・三条市のお話です。
「新潟県三条市」「三条市役所 食育推進室」田村直(なお)さんにお話をお伺いします。
◎ はじめに新潟県三条市に関して教えて下さい。
新潟県のほぼ中央に位置し、農地も多いが包丁や工具などの金物の工業が盛んで、
全国的にも有名です。
◎ 三条市では町をあげて、給食の主食はお米にしているそうですね。
「米飯(べいはん)給食の完全週五回」として、月曜から金曜までの給食の主食は、
すべて地元産のコシヒカリを使っています。
◎ この取り組みをはじめたきっかけを教えて下さい。
取り組みを始めたのは平成15年から。減反が進む中、お米の生産量&消費量が
伸び悩み生産者から給食でぜひ使って欲しい。
保護者からも米所三条市なんだから、給食には地元のお米を使うべきだという
意見が寄せられました。
◎ お子さんたちの反応はいかがでしょうか?
最初は小中学校合わせて22校でスタート。お米は地元のJA協力のもと、提供
されました。毎日お米だと残す量が増えてしまうかもしれない・・・という考え
があったが、実際には食べ残しは増えなかった。
おおむね好評で、当時、田村さんは給食を担当しており、そのような意見を
ダイレクトに聞きました。
◎ お米の給食になって、新たなメニューも登場したそうですね。
「たまごみそ」地元で昔から食べられている味噌で味付けをした炒り卵。
「手作りふりかけ」既製品ではなく、手作り品。
また、少量の副菜がでるようになり、品数が増え給食がにぎやかになった。
みんなは「副々菜」と呼んでいます。
◎ おしまいに、田村さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。
ご飯がおいしいと思える食事を摂ること。
投稿者 joqr : 12:45
2010年8月29日 ゲストは社会学者で「居酒屋を通じた社会研究」をされている橋本健二さん。
橋本健二さんは1959年、石川県のお生まれ。
東京大学・大学院博士課程を経て、研究者としてのキャリアを
スタート。2002年からは武蔵大学社会学部教授を勤められて
います。
これまでに多くのご本を書かれていますが、なかでも
「居酒屋ほろ酔い考現学」は居酒屋から見えてくる日本社会に
ついて記された一冊で、話題を呼んでいます。
各所の居酒屋の特徴や歴史、
階層論的にみた居酒屋を取り巻く状況をご説明いただきました。
投稿者 joqr : 12:38
2010年8月30日 夏の終わりに
しかし、暑い!八王子は、34度が続いている。
暦の「立秋」と、体感する秋はどんどん距離が開いていく・・・
ここ数年、そう思う。
久しぶりに脱走に成功した我が家のネコは
外の暑さに耐えきれず、2分で詫びの声を出しながら網戸をこじ開けた。
好物の雑草があまりに高温になっていたからである。
猫舌とはよくいったものだ。
『春は名のみの風の寒さや・・』早春賦の一節だ。
『早秋譜』という作品があるならば
現代は『秋は名のみの外の暑さや』だ。
朝起きると汗ばんでいる。
布団を干すと、大汗。
ご飯を食べて、汗とまらず。
水シャワーで救われる。
ネコ砂を買いに行ってまた汗。
帰ってきて水を飲み、汗。
布団を取り込み、大汗。
水シャワーで一休み。
体重計に乗る。
減らない。
夕方5時をまってビールのプルトップに手をやる。
う~ん、甘い!
ツクツクホウシが鳴いている。
嫌ではないな・・・この生活。
夜は虫が喧しいくらい元気だ。
秋はすぐそこに来ているのだろうか・・・。

救い

夏は名のみの

夏の終わりに
投稿者 joqr : 10:15
2010年08月23日
2010年8月22日 ゲストは鈴木のりたけさん。
今週のお客様は、いま話題の絵本「しごとば」「続・しごとば」
の著者、鈴木のりたけさんです。
鈴木のりたけさんは1975年、静岡県・浜松市のお生まれ。
グラフィックデザイナー、イラストレイターとして活躍をされ、
「TOKYO イラストレーション 2007」に入賞を
されています。
現在発売中の絵本「しごとば」は、新幹線運転士、
すし職人、歯医者さんなどの仕事場を、ユーモラスなイラストで
紹介した一冊です。
今回は鈴木さんのいろいろな「しごとば」取材や絵本執筆のエピソードを伺いました。
投稿者 joqr : 14:28
2010年8月22日 近江舞子いちご園
日本各地に多くの観光農園がありますが、ご紹介するのは、農家のお母さん方が
運営しています、「露地栽培」にこだわりました観光農園です。
(※露地栽培=ハウスではない)
滋賀県・大津市「近江舞子いちご園」代表の田中勝江さんにお話をお伺いします。
◎ はじめに「近江舞子いちご園」に関して教えてください。
今から28年前に始めた観光農園。地域の農家のお嫁さんを中心にはじまりました。
当初は6名ではじめたが、現在は20人近くで営業。イチゴや野菜の収穫体験だけでは
なく、最近ではジャムなどの加工品も販売しています。
◎ 農園は露地栽培にこだわってるそうですが・・・?
山から吹き込む強い風の影響で、ハウスが建てられません。春はいちご狩り、秋には
落花生やいも掘り体験ができます。露地栽培を行うことにより、お客さんに季節ごと
の野菜の旬を伝える事ができる効果があります。
◎ どんなお客さんが多いのでしょうか?
住所は滋賀県ではあるが、京都や大阪からも、車を使い30分ほどで来られるため
幼稚園児や小学生が遠足で、体験学習にやってきます。
◎ お子さんたちの反応はいかがでしょうか?
農園では、ただ収穫するだけではなく収穫後、田中さんがイチゴや野菜に関して話をします。
紙芝居などにしてわかりやすく説明するように心がけています。
元気いっぱいで、言うことをきかないがみんな熱心に話を聞いてくれます。
◎ 今後の予定を教えてください。
9月に入ると6月に植えた落花生やさつまいもの収穫体験がはじまります。
それが終わると、今度はイチゴの定植を行います。1年中、作業は続きます!。
◎ おしまいに、田中さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。
自分たちが作った野菜など、生産者が分かる食べ物を食べることです。
投稿者 joqr : 14:14
2010年8月23日 少年の思い出
6月に地球に帰還した探査機「はやぶさ」のカプセルを見てきた。
7年かけて小惑星「イトカワ」までを往復、60億キロに及んだはやぶさの壮大な旅。
「丸の内オアゾ」で一般公開。
テーマは『君が私たちに残してくれたもの』
初日の15日は、朝から約1800人が列を作り、入場者数は8434人に上ったという。
18日午後2時、1時間は並ぶ覚悟で行ってみた。
30メートル程の列には意外にも白髪交じりの60代男性が目に付く。
その目は少年のごとく輝いている。
最後尾で整理券を受け取った。
チラシを2種類受け取り、回転寿司の皿の速さで進んでいく。
「夏休み中の子供たちに見せたい!」
そんな主催者の意図通り、小学生も多くいる。
中にはほとんど興味の無い子供もいた。
「ねえ、ママ~、まだ見られないの~?」
「○○ちゃん、みんな並んでいるでしょ!静かにしなさいっ」
「ねえ、何があるの~?」
「カプセルよ!宇宙を旅してきたの」
「それみたら何食べるの~?」
「○○、見てからよ」
「なんでよう!もう熱中症になる~」
屋内である。確かに外は暑いが、ここは涼しいのだ。
母親の表情から爆発を必死で堪える気を読み取った。
子供のためを思い連れてきたのに・・・親の心子知らずである。
私もきっと同じことをしていたのだろうなあ。
予想より早く、17分で入り口に。
俄か作りの選挙投票所という感じ。
電子機器、
中華なべを二つ合わせたようなカプセルなどがあわせて3つ並んでいる。
1970年、大阪万博でみたアメリカ館の『月の石』を思い出した。
「これが・・・」あのときの気持ちと同じだ。
回転寿司のスピードで展示会場を出た。
ごねていた子供が母親に言った。
「チャーハン食べたい!」
ポスターの副題が目に入った。
『はやぶさから、あきらめない強さを子供たちに伝えませんか?』
母親はある意味目的を達成したと感じた。
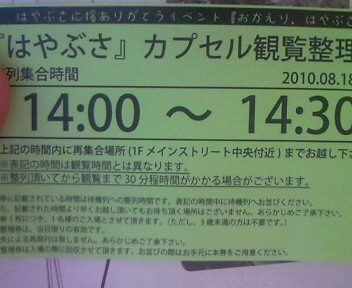
あきらめない
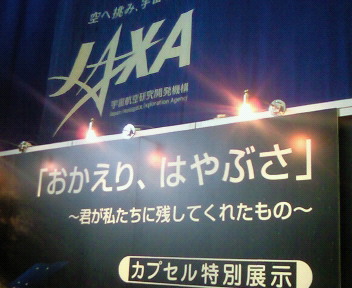
少年の思い出
投稿者 joqr : 10:00
2010年08月16日
2010年8月15日 ゲストはアグネス・チャンさん。
今週のお客様は、歌手でエッセイスト、そしてユニセフ大使でも
いらっしゃいます、アグネス・チャンさんです。
アグネス・チャンさんは1955年、香港のお生まれ。
14才のとき香港で歌手活動をはじめられ、72年、17才のときに「ひなげしの花」で日本の歌謡界にデビューをされました。
78年にカナダ・トロント大学を卒業。
80年代のなかばから、芸能活動にくわえて、ボランティア活動をはじめられ、現在は日本ユニセフ協会の大使もつとめられています。
今年の2月にはユニセフ協会の大使として、アフリカ・ソマリアの視察をされました。
今回はそのソマリア現状、避難民キャンプのお話を伺いました。
投稿者 joqr : 14:26
2010年8月15日 大根の実
日本ではたくさんの野菜が栽培されています。地方に行くと、「こんな野菜あったの?」と驚くことも。
今日は、山形県の農産物加工所で「大根の実」というちょっと変わった商品を販売しているというお話しです。
「山形県上山市」「ジェイエイあぐりんやまがた」「上山農産加工所」の
落合しげ子さんにお話をお伺いします。
◎ はじめに山形県・上山市に関して教えてください。
山形県の南東部、自然豊かな土地で、夏はサクランボ狩りでにぎわう。
他に桃やナシ、ブドウなども特産。最近では映画「おくりびと」の撮影場所にもなった
◎ そちらの加工所は、ずいぶん歴史があるそうですね!
加工部会は、30年以上の歴史を持ち、普段は食べないような変わった野菜も出荷しています。
農家の奥さんを中心に30人ほどで運営しており、現在は株式会社として組織しています。
◎ 噂の「大根の実」。どのような商品でしょうか。
あまり市場には出回らない「大根の実」を冷凍して出荷しています。大根の実は、
花を咲かせて「さや」の部分を収穫。とったらすぐに茹でて、冷凍保存する。
冷凍保存のため、季節に関係なく1年中出荷できます。
◎ 「大根の実」は、どのような味がするのでしょうか?
さやの部分も大根の味がほのかにする。地元では昔から食べられており、味噌漬にしたり
ごま和えにして食べます。
◎ 他にはどのような商品がありますか?
自分たちが近くの山で採ってきた「うこぎ」(山形の伝統野菜)」「またたび」なども販売。
大根の実同様、採ってきたらすぐに茹でて冷凍保存する。甘酢で付けた「さくらんぼ漬」も人気。
全国への発送にも対応しています。
投稿者 joqr : 14:08
2010年8月16日 S8
65回目の終戦記念日、八王子は猛暑日となった。
近くの公園から「油」の騒々しい声がする。
「あの日、蝉だけは元気だったのよ・・」
遠い目をして母が呟いた。
1945年8月15日、
日本は37年から戦争に突入し、
戦死者230万、民間で犠牲になった人80万
合わせて310万人の命が奪われた。
母が聴いたあの時の蝉は、何を思って鳴いていたのだろう。
アブラゼミが幼虫として土の中で過ごす歳月は長く、
平均6,7年と言われている。
殻を破って飛び出した地上での寿命はわずか2~3週間あまり。
限られた時間の中、オスはメスへのラブソングを歌いあげるという。
310万の御霊は、「平和」を合唱しているに違いない。
庭のそこここにある「殻」を手にした。
力を入れれば壊れてしまうその足は
草や木にしっかりとしがみついていた。
私達がしがみついてでも守らなければならないものは・・・。

S8
投稿者 joqr : 10:27
2010年08月09日
2010年8月8日 ゲストは山崎充哲さん。
ゲストは多摩川の再生に関する活動をされている山崎充哲さんです。
山崎充哲さんは1959年、神奈川県・川崎市のお生まれ。
日本大学で水産学を学ばれたのち、環境アセスメントのお仕事を
され、全国の河川や海で、生き物の調査をされてきました。
近年は、多摩川を再生に関する活動に従事され、特に多摩川の
鮎に関して、詳しい研究をされています。
「多摩川の専門家」山崎充哲さんに、
多摩川に生きる魚のお話し、また、多摩川から見えてくる
環境問題についてお話しをお伺いしました。
投稿者 joqr : 14:25
2010年8月8日 喜多方市立熱塩小学校 鈴木卓校長先生
子供たちに農業を身近に感じてもらおうと「食育」の授業を行っている学校が
増えて来ていますが福島県・喜多方市では、町を挙げて「農業科」という授業を
スタートさせているそうです。一体どのような授業なのでしょうか?
福島県・喜多方市「喜多方市立熱塩小学校」の「鈴木卓校長先生」にお話をお伺いします。
◎ はじめに熱塩小学校と喜多方の街に関して教えて下さい。
熱塩小学校は全校65名の小学校です。地元の喜多方市は、古くから農業を主として
地場産の米や大豆は酒、みそ、しょうゆなどの醸造業も栄え、今も多くの醸造蔵が残っています。
◎ 小学校には「農業科」という授業があるそうですが・・・?
2007年度から小学校の授業に「農業科」を新設。農業体験を取り入れる動きは
広がっており、現在は1~2年生は生活の時間。3~6年生は総合学習の時間。
年間42時間ほど割り当てています。
◎ 授業ではどのような事をするのでしょうか?
保護者や農家から選ばれた支援員が配置され、実習用の田畑は近くの農家から借ります。
子供たちは土作りから行い、収穫した野菜や米で料理や餅をつくり、授業を支えてくれた地域の人を招いて収穫祭を開きます。今年も9月末に「とうもろこしパーティー」を開催します。
◎ この授業をはじめたきっかけを教えて下さい。
農村地帯でありながら身近にある農業を知らない子どもが増加。農作業を通じて「地域の人たちに支えられていることに、子どもたちに気づいて欲しい」と考えて実施します。
◎ 生徒のみなさんの反応はいかがでしょうか?
自分たちの野菜を給食センターに持っていく事もあり食べ物に対する意識が変わりました。
校長先生は農作業を通じて、食べ物の事だけではなく、地元の方との繋がりをぜひ学んで欲しいと思っています。
◎ おしまいに、鈴木先生にとっての「よい食」とは何かを教えてください。
喜多方市では、箸の持ち方、食事のマナーなども町を挙げて行っています。
自分自身も気を付けています。
投稿者 joqr : 14:07
2010年8月9日 いざ出陣!
金曜から日曜日にかけて八王子祭りがあった

いざ出陣!
昭和36年(1961年)「三万人の夕涼み」として、富士森市民球場で第1回市民祭として始まり今年で50回を迎えた「八王子まつり」

夏の獅子舞

祭り人の背中
キリのいい今年、記念として、
8月7日(土)甲州街道に上(かみ)地区、下(しも)地区
山車19台が一堂に集結する「上下山車総覧」が行われた。
八王子の山車の歴史においても「初」となる行事
明治・大正・昭和そして平成製の作品。
また、八幡町1・2丁目の山車人形「神武天皇」が92年ぶりに山車にのせられ巡行するとのこと。のぞきにいった。

92の年月を経て・・・
午後2時から、JR八王子駅から北に延びる並木通りに交わる甲州街道から、
追分の交差点までに交通規制がかかった。
いつもは、バスやトラックが絶え間なく往来する動脈である。
その甲州街道が「民謡流し」の舞台に。
4時から地元の「連」総勢4000人が八王子音頭はじめ地元八王子を気持ちよく踊った。

緑のたぬきはいずこ?

誘笑
西の空が綺麗に茜に染まりかけてきた頃、ふと街道に交わる路地を見ると、
太く長い綱の後ろに、歴史ある「山車」が今か今かと合図を待っていた。
太鼓や鳴り物をいつでも響かせることができるよう、バチを握りしめ、
面をつけた演じ手は、正面に手を突き出しその時を待っていた。
緊張感が辺りに広がる。
先導者が大きな「○」を作った。
山車に乗っている野郎どもが笑顔に変わった。
甲州街道に繋がる路地から、1つまた1つ、合計19台の山車が姿を見せる
御輿の活気とは違った厳かな佇まい。笛や太鼓そして山車ごとに違うキャラクター。
伝統文化の競演。
山車が集合場所に勢揃いした時には、
空は輝きを消し、提灯の明かりに主導権を譲っていた。
町民はこの日を目指して稽古をしてきた。
長はみんなを束ねた。
お揃いの半纏をはおり、山車の後ろからゆっくり歩く70代のまとめ役。
早くも感動と安堵感から鼻が垂れている。
ぐっと来た。
屋根に乗る役も順番。太鼓や笛も疲れたら後が代わる。
困ったときは「お互い様」、喜びは「かわりばんこ」。皆平等。
祭りという「ハレ」を目標に日々の生活が潤っていく・・・。
それは自分たちだけでなく、周囲をも幸福感に染めていく。
八王子の伝統に感謝!

金獅子

19の太陽
投稿者 joqr : 10:15
2010年08月02日
2010年8月1日 ゲストは「暮らしの手帖」社の横山泰子さんです。
昭和23年に創刊された生活情報雑誌の草分け「暮らしの手帖」社の横山泰子さんです。
横山泰子さんは昭和30年、神奈川県のお生まれ。
学習院大学を卒業後、「朝日新聞社」勤務を経て、平成5年、
「暮らしの手帖」社に入社。
平成16年から平成22年7月まで、「暮らしの手帖」社の代表取締役社長を務められました。
横山泰子さんに、創刊から60年以上、かわらぬスタイルを貫かれている雑誌「暮らしの手帖」
についてお伺いしました。
投稿者 joqr : 14:22
2010年8月1日 トマトベリー
トマトはわたしたちに特に馴染み深い野菜ですが・・・。
みなさんは「トマトベリー」と呼ばれている、
「イチゴのようなトマト」をご存じでしょうか?
今日はその鳥羽とベリーについて、「埼玉県・加須市」「JAほくさい」
「組合員」の松本進さんに話をお伺いします。
◎ はじめに埼玉県・加須市に関して教えて下さい。
加須市は埼玉県北部。ちょっと北に行くと、利根川があり、群馬県の邑楽・富岡に近い。
私がいるのは加須市の中でも、旧・大利根町地区。今年の3月に市町村合併で、
加須市に統合されました。以前からイチゴの栽培が盛んな土地です。
◎ トマトベリーとは、どのような野菜なのでしょうか?
トマトなのにハート型をしておりスイカ並みの甘さが特徴。通称「トマトベリー」です。
名前の由来は、「トマト」と「ストロベリー」の語呂合わせから来ています。
私のグループでは、イチゴぐらい甘い事から「苺トマト」として売り出しています。
◎ 苺トマトを栽培し始めたきっかけは?
元々私さんの家ではプチトマトの栽培を行っていました。今から2年前に地元の種屋
さんの勧めで、苺トマトの栽培に着手した。
地元の「ふる里農業創生センター」や町長の協力もあり栽培をはじめました。
◎ 何人ぐらいの方が、栽培をしているのでしょうか?
最初はたった一人で作り始めたが、今年で2年目になり賛同者は4名。人数が増え、
年間を通じて季節に関係なく1年を通じて出荷できるようになりました。
◎ 出荷するに当たって、苦労している部分はありますか?
苺トマトは、完熟させてから出荷しています。甘く、本来の味が出るように・・・。
そのタイミングを計るのが一番気を遣う。そのまま食べたり、サラダにするのがおすすめです。
ぜひみなさんに一度食べてもらいたい!
◎ おしまいに、松本さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。
自分たちが作った野菜など 何でもおいしく食べる事。
投稿者 joqr : 14:00
2010年8月2日 未来のプロゴルファー
日曜、久しぶりに小さな旅をした。
茨城県笠間市で、未来の石川遼、宮里藍等を目指す、高校生のゴルフ大会開会式に行ってみた。
今をときめく、男女プロゴルファーの大部分が参加経験のある大会。
全英女子ゴルフで活躍の、上田桃子、有村智恵、宮里藍、横峯さくらは、24回大会で、団体戦上位三校のそれぞれメンバーだ。
男女前回優勝、福岡・沖学園、女子は宮城の名門・東北高校優勝旗返還から会は始まった。
野球に比べ、選手の体格はごく普通。
しかし、努力の汗は人一倍流している。
全国各地区を勝ち上がり、男・38校 、女・17校 が、文部科学大臣旗の争奪を3日から繰り広げる。
開会式で驚いたことがあった。
サッカーワールドカップ南アフリカ大会の影に隠れる形となったが、同じ時期に18歳以下のゴルフ世界団体戦が、日本で行われていたのだ。結果は、強豪をおさえて日本の優勝!
その報告が行われた。
日本ゴルフの実力をまざまざと見せ付けた大会となった。
メジャー一歩手前のドラマ、色々あるものだと痛感。夕方五時過ぎ、帰りの常磐線、奮発して各駅停車のグリーン車に乗ってみた。
1000円の贅沢である。
これがよかった!
二階建の一階部分、私独占。
土浦で15分の停車という時間を利用し、ホームでそばをすすった。
月見そばは熱かった。
味よりも、時間内完食の安堵感が先に来た。缶チューハイもゲット!
急いで座席に戻り、プルトップを引いた音が爽やかだった。
昔は、ホームの停車時間で駅弁やお茶を買っていた。あのスリル感、もう味わえないと思っていたのに。
昭和の鉄道旅行感覚を味わえた。
外に出るのはいいもんだ!そう思った。
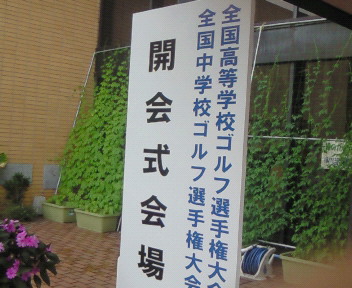
未来のプロゴルファー

打出のー

グリーン車独占

土浦の夕日

これは〓
投稿者 joqr : 10:46